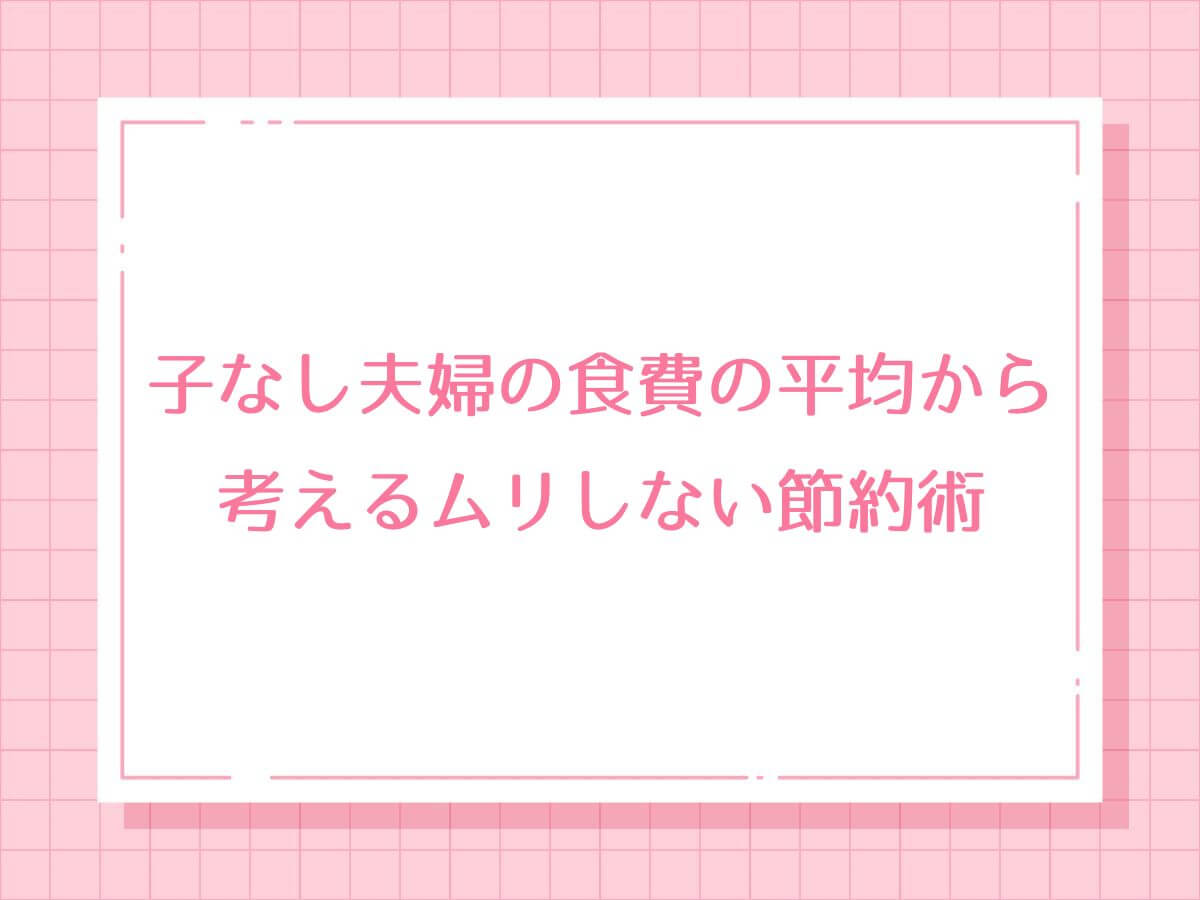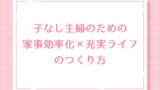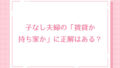夫婦だけで暮らしているあなたは、食費の使い方が「これでいいのかな?」と、ふと迷うことはありませんか。
二人暮らしで3万円に抑えている人もいれば、5万円、6万円と少し余裕を持たせている家庭もあり、平均や正解が見えづらいのが現実です。
また、外食の回数やお弁当の有無、共働きかどうかなどによって、毎月の食費は大きく変わります。
この記事では、子なし夫婦の食費の平均や内訳を公的データに基づいてわかりやすく整理し、さらに年代やライフスタイルによる違い、実際の声までを紹介しています。
二人暮らしの食費で、外食抜きでどこまで抑えられるのか、2人暮らしで食費4万は高いのか、50代夫婦2人の食費はどう違うのか…。
そんな日々の小さな疑問や不安に寄り添い、「わが家にちょうどいい食費バランス」を見つけるためのヒントをまとめました。
他の家庭と比べすぎず、でも無理なく気持ちよく暮らすために…。
最後の方では筆者(しずく)の家庭の食費のことについてもお伝えします。

子なし主婦のあなたの食費のヒントにしてください。
子なし夫婦の食費の平均はいくら?リアルなデータと世間の声から検証

- 夫婦2人の1ヶ月の食費はいくらですか?公的データで見る平均額
- 食費平均2人家族の内訳はどうなっている?
- 二人暮らし食費外食抜きの相場感を知ろう
- 子なし夫婦の食費を3万円に抑えるのは現実的?
夫婦2人の1ヶ月の食費はいくら?公的データで見る平均額
夫婦二人で暮らす場合、1ヶ月あたりの食費はどの程度が一般的なのでしょうか。
総務省の「家計調査(2022年)」によれば、二人暮らし世帯の食費平均は67,573円となっています。

これは外食を含んだ金額であり、地域や世帯の年齢、収入によってもばらつきがありますが、おおよその目安として参考にできるのではないでしょうか。
地域差による食費の違い
地域によっても食費には差が見られます。
たとえば関東地方では月平均81,406円と高めですが、沖縄地方では66,257円と全国平均よりやや低めの傾向です。
これは物価や外食文化の違い、交通インフラによる食材の価格差などが影響しています。
年齢によって変化する傾向
年齢別に見ると、40代〜60代の夫婦では食費が最も高くなる傾向があり、8万円を超えるケースも珍しくありません。
一方で、若い世代(30代以下)は平均6万3千円台と比較的低めです。これは食事の量や外食頻度、健康志向の違いなどが関係していると考えられます。
収入が多い世帯ほど食費も高くなる傾向
また、世帯収入が上がるほど食費も増える傾向にあり、年収が1,000万円を超える世帯では月に10万円以上を食費に充てているケースもあります。
これは高価な食材や外食の頻度が影響しています。
一方で、年収が300万円台の世帯では5万〜6万円に抑えられていることが多いです。

このように、夫婦2人暮らしの食費平均はあくまでも目安であり、ライフスタイルや地域性によって柔軟に考えることが大切です。
食費平均2人家族の内訳はどうなっている?
食費の平均額がわかったところで、実際には何にどれくらいお金を使っているのか、その内訳も見てみましょう。
公的データによると、67,573円という平均額は以下のような項目に分かれています。
内訳と費用一覧
| 項目 | 平均支出額(円) |
|---|---|
| 穀類(米・パンなど) | 5,371 |
| 魚介類 | 5,980 |
| 肉類 | 6,058 |
| 乳卵類 | 3,529 |
| 野菜・海藻類 | 8,522 |
| 果物 | 3,316 |
| 油脂・調味料 | 3,389 |
| 菓子類 | 5,416 |
| 調理食品(惣菜など) | 10,396 |
| 飲料 | 4,459 |
| 酒類 | 3,462 |
| 外食 | 7,675 |
(こちらの表は2022年総務省統計局が2025年4月に発表した最新の「家計調査」を元にしています。)
自炊中心の食費が多くを占める
上記の内訳を見ると、「調理食品」と「外食」で約1万8千円程度を占めています。
つまり、残りのおよそ5万円ほどが日常的な自炊のための食材費であることがわかります。
野菜や肉、魚などの生鮮食品に多くの費用がかかっているのは、健康を意識して自炊を続けている世帯が多いためと考えられます。
意外と多い「お菓子」「飲料」「酒類」の割合
菓子類・飲料・酒類を合わせると約1万3千円にものぼります。これは全体の2割近くを占めており、嗜好品の存在が食費に与える影響の大きさがうかがえます。
特に在宅時間が増えた近年では、家で楽しむお酒やおやつが増えた家庭も多いのではないでしょうか。
「節約するならどこから?」を考える材料になる
こうして内訳を見ることで、「調理食品の購入を減らして自炊を増やす」「お菓子やお酒の回数を見直す」といった節約の方向性も見えてきます。
食費を見直すときは、全体の金額だけでなく内訳もチェックすることが効果的です。
二人暮らし食費外食抜きの相場感を知ろう
食費を見直す際、「外食を除いた自炊ベースの金額」は、多くの家庭が関心を持つポイントです。
夫婦二人暮らしの場合、外食を含めた平均的な食費は、最初の方でもお伝えしたように、約6万7千円前後というデータがありますが、外食を含まない場合の相場感はもう少し低くなります。
平均的な家庭では外食費は月7,000〜8,000円程度
総務省の家計調査によれば、二人世帯の外食費は約7,600円となっています。
これを差し引いて考えると、自炊・食材購入にかかっている費用は約6万円前後というイメージになります。
自炊中心の家庭では4万〜5万が現実的なライン
実際の体験談や家計管理ブログなどを見ると、外食をほとんどせず自炊メインの家庭では「月4〜5万円の範囲」でやりくりしているケースが多く見られます。
これは以下のようなポイントに影響されます。
- 買い物の頻度を週1〜2回に限定している
- 業務スーパーや特売品の活用
- 作り置きや冷凍保存で食材ロスを防いでいる
また、家庭によってはお弁当を毎日持参することで外食代をゼロに近づけたり、米や調味料をふるさと納税でまかなっている人もいます。
こうした工夫によって、外食を含まない実質の食費を「4万円前後」で抑えている家庭も少なくありません。
あくまで“自分たちの食生活に合った金額が基準
たとえば、毎日しっかり三食を自宅で用意する家庭と、朝食は軽く・昼はお弁当・夕食だけしっかり作る家庭では、必要な食材量や費用も変わります。

自分たちのライフスタイルにあわせて、まずは「1日あたりの食費」がいくらかかっているかを把握するところから始めてみましょう。
子なし夫婦の食費を3万円に抑えるのは現実的?
「食費は3万円以内に収めたい」と考える方は少なくありません。
特に貯蓄や家の購入など、明確な目的がある家庭では節約志向が強くなります。
では、夫婦2人暮らしで月3万円の食費は現実的なのでしょうか。
月3万円の食費=1日あたり約1,000円
まず、3万円でやりくりする場合、1日あたりで使える金額は1,000円。
二人分でこの金額ですので、1食あたりに換算すると300〜350円以下で抑える必要があります。
飲料代や調味料、お菓子類などを含めると、かなりタイトな設定になります。
実現可能ではあるが、相当な工夫が必要
ネット上の体験談やSNSを見ると、「月3万円」を達成している家庭も確かに存在します。ただし、その多くが以下のような工夫を徹底しています。
- 肉や魚はまとめ買い&冷凍保存
- 旬の野菜や安価な食材を中心に献立を組む
- お菓子・お酒・嗜好品はほとんど買わない
- 米や調味料はふるさと納税や特売で補う
- 外食・テイクアウトは月0〜1回に抑える
つまり、節約を目的に意識的に取り組まないと、月3万円という水準は達成が難しいといえます。
なお、食事の楽しみや健康志向を重視したい人にとっては、ややストレスの多い金額設定になるかもしれません。
「節約に振り切る」期間を決めるのもおすすめ
どうしても3万円に収めたい場合は、一定期間だけ節約に集中する「期間限定ルール」を設けるのも効果的です。
「半年だけ食費を絞って貯金に回す」など、目標が明確であれば継続もしやすくなります。
一方で、「そこまで厳しくしなくてもよい」と思える方は、3万〜4万円の範囲で自分たちに合った無理のない予算を設定するのも一つの考え方です。
子なし夫婦の食費の平均から考えるわたしが大切にしていること

- 共働き夫婦食費のリアル:ストレスなく続けるための工夫
- 夫婦のみの食費の考え方:シンプルだけどゆとりある暮らし
- 私(筆者)が考える「節約」と「満足」のちょうどいいバランスとは
共働き夫婦食費のリアル:ストレスなく続けるための工夫
共働き夫婦にとって、毎日の食費を抑えつつ無理なく暮らすことは、大きな課題のひとつです。
仕事で忙しい日々の中、完全自炊を続けるのはなかなか難しく、「節約」と「手間」のバランスをどう取るかがポイントになります。
次に、共働き家庭でよく見られる現実的な工夫をご紹介します。
「平日はシンプル、休日はしっかり」で無理のない食生活に
平日の夕食は、炒め物や丼ものなど、手間のかからないメニューにしている家庭が多いです。
調理時間を30分以内におさえるだけでも、仕事終わりのストレスは大幅に軽減されます。
一方で、休日は少し丁寧に料理をして冷凍ストックを作ったり、外食を楽しむ時間にあてたりと、緩急をつけることで「やらなきゃいけない」から「自分たちで決めた食生活」へと意識が変わります。
便利アイテムやサービスの併用で効率アップ
すべてを手作りにこだわらず、冷凍野菜・カット野菜・下味冷凍・ミールキットを取り入れるのもひとつの方法です。
また、生協やネットスーパーを活用することで、買い物の時間も短縮できます。買い物に行かない日があるだけでも、気持ちに余裕が生まれます。
ストレスなく続けるための小さな工夫
- 毎週のメニューをざっくり3〜4パターン決めておく
- 週末にまとめ買い&下ごしらえ
- お弁当は冷凍食品をうまく活用
- 朝食やランチはパターン化して手間を減らす
上記は食事の準備をストレスなく続けるための工夫例です。
共働き世帯は完璧を目指さないことが大切です。
「お惣菜に頼る日があってもいい」「外食もストレス解消になる」といった柔軟な考え方を持つことで、食費のやりくりも前向きに取り組めるようになります。
夫婦のみの食費の考え方:シンプルだけどゆとりある暮らし
子どもがいない夫婦二人の生活では、食費の捉え方が大きく変わります。
家族の人数が少ない分、生活の自由度が高く、「何にどれだけお金をかけるか」を自分たちで選べるのが特徴です。
その中で、「食費を削りすぎず、楽しみながら暮らす」ことを意識している家庭も多く見られます。
一人一人の「満足感」に合った食費設計
二人だけの暮らしでは、1日3食すべてを手作りしない家庭も少なくありません。
たとえば「朝食はパンとコーヒーだけ」「昼はおにぎりとスープ」「夜は自炊でしっかり」など、ライフスタイルに合わせて自然と食費も調整されていきます。
また、お互いの好みや満足度を尊重することが、無駄なストレスや無理な節約を防ぐことにもつながります。
節約だけに縛られない「食のゆとり」も大切に
たとえば、平日は質素に過ごしていても、週末にはちょっと良い食材を使って自炊したり、お気に入りのレストランで外食を楽しんだりする人もいます。
これも、夫婦のみだからこそできる“贅沢”のひとつです。
毎日を頑張る自分たちへのご褒美と考えれば、こうした出費も単なる消費ではなく、「満足感」へとつながります。
家計全体のバランスの中で食費を見る
夫婦のみの暮らしでは、「節約=食費を削る」と決めつけず、住居費・保険・通信費などの固定費とのバランスを取りながら考えることが大切です。
自炊を頑張っても、固定費が高ければ意味が薄れてしまいます。
食費は毎日の生活に直結する支出だからこそ、気持ちよく使えるラインを見つけることが、豊かさにつながります。
私(筆者)が考える「節約」と「満足」のちょうどいいバランス
最後に子なし夫婦歴33年のわたし・しずくの考えをお伝えしたいと思います。
食費に関しては、「いかに安く抑えるか」だけを目標にしてしまうと、楽しみや健康を犠牲にしてしまうことがあると思います。
私自身、毎月の食材購入だけでも5〜6万円はかかっています。無添加やオーガニックのものを選ぶこともあり、全体としては平均よりも高いかもしれません。
「食費は生活の中の楽しみ」という価値観
夫が美味しいもの好きということもあり、時々、夫が自分で食材を買ってくることもあります。
そうなると、食材費だけで我が家は6万円を超える月もありますし、外食を含めると食費は10万円近くになることもあります。

でも私たちにとって「美味しいものを食べること」は、日常生活の中の大切な楽しみのひとつです。
他を抑えて、食にゆとりを持つ選択もある
私は普段、あまり外に出る機会が多くないため、化粧品代や洋服代、アクセサリー代などにはほとんどお金を使いません。高級ブランドに興味があるわけでもないので、自然とその分の支出が少なくなっています。
だからこそ、その分「食」にはある程度お金をかけても良いのではないかと考えています。
「3万円で抑えるべき」は人それぞれの価値観
かつては私も共働きで、郊外の安い八百屋に行ったり、農家さんが路上で売っている野菜を買ったりして、できるだけ節約しようとしていました。
30年近くも前の話ですが、当時でも食費は2人で3万円程は度かかっていた記憶があります。
今は物価が上がっているため、当時と同じやり方をしても、3万円以内に収めるのはかなり難しく感じます。
「健康」と「安さ」をどう両立させるか
食費を安くあげられるに越したことはありませんが、「安かろう悪かろう」という言葉があるように、安さを追いすぎて品質を妥協するのも考えものです。
とくに添加物など、健康への影響を考えると、単に価格だけで食材を選ぶことには抵抗があります。
節約は大事ですが、それによって失うものが大きくならないようにしたいと感じています。
大切なのは「自分たちらしい基準」
結局のところ、他人と比べて「うちは使いすぎかな?」「もっと節約しなきゃ」と思うよりも、「自分たちはどう暮らしたいのか?」「どんな食生活が心地よいのか?」を考えるほうが大切だと感じます。

食費の使い方は、その家庭の“ちょうどいいバランス”がそれぞれにあるはずです。私たち夫婦にとっては、美味しさと安心感を得られる食生活がその基準です。
【まとめ】子なし夫婦の食費の平均と暮らしに合わせた考え方
今回の記事のまとめです。
- 子なし夫婦の1ヶ月の食費の平均は約67,000円程度
- 地域差があり、関東では8万円超、沖縄では6万円台が目安
- 年齢が高くなるほど食費は増える傾向がある
- 高収入世帯ほど食費も高くなる傾向にある
- 食費平均の内訳では調理食品と外食で約18,000円を占める
- 生鮮食品や自炊用の食材に約5万円が使われている
- お菓子・飲料・酒類だけで月13,000円前後かかるケースもある
- 外食を除いた自炊のみの食費は4万〜5万円が相場
- 自炊中心でも買い方や保存方法の工夫が節約の鍵となる
- 月3万円以内でのやりくりも可能だが継続には強い意識が必要
- ふるさと納税やまとめ買いの活用でコストを抑える家庭も多い
- 共働き夫婦は「手間を減らす工夫」と「柔軟な考え方」が重要
- 子なし夫婦は価値観に応じて「楽しむ食費」を重視する傾向もある
- 健康や満足度を重視し、あえて食費を抑えすぎない家庭もある
- 大切なのは他人と比べず、自分たちに合った食費のバランスを見つけること
今回の記事、お役に立てたら嬉しいです。
ありがとうございました。
こちらの記事も参考にどうぞ♪
【年金・家計・金融情報について】
本記事は統計や一般的な相場をもとにした情報です。年金制度や税制・投資商品は法改正等により内容が変わる場合があります。
掲載情報は記事公開日時点の概要であり、日本年金機構・厚生労働省・金融庁などの公式発表 を必ずご確認ください。
最終的なご判断は読者ご自身の責任においてお願いいたします。