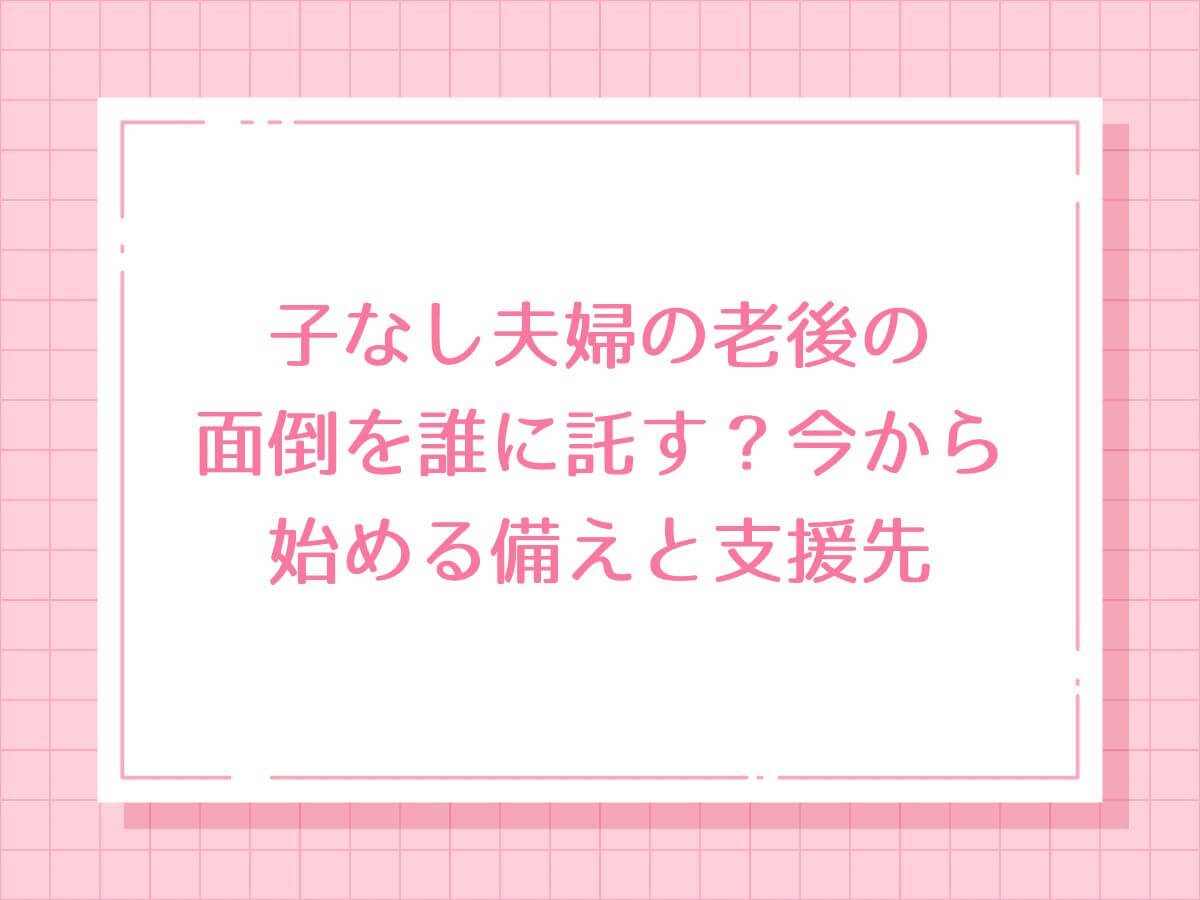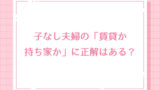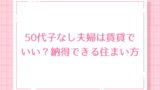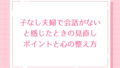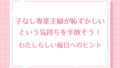「子なし夫婦って老後、大変じゃないの?」と周りから言われたことはありませんか?
「子なし夫婦の老後は悲惨だ」という批判めいた発言もSNSで目にすることがあります。
本当にそうなのだろうか?と、そんな不安を胸に、ネットで情報を探している方も多いのではないでしょうか。
みじめな老後を避けたいという気持ちと、幸せに年を重ねたいという願いは、どちらもとても自然な感情です。
老後の面倒を誰が見てくれるのかという問いに、正解はひとつではありません。ですが、少しの知識と少しの備えで、その不安をやわらげることはできます。
年金や老後資金、住まいのこと、夫婦ふたりの暮らしの形、そして将来の支え方や託し方まで。現実を知りながら、自分たちらしい幸せの形を見つけていくことがとても大切です。
この記事では、子なし夫婦の老後の面倒を誰に託すのかというテーマを軸に、具体的な支援制度や備え方について解説していきます。
子なし夫婦の老後の家や住まい選びに迷っている方、老後対策としてどんな準備ができるのか知りたい方、現実の中でどうやって不安と向き合えばよいのか悩んでいる方にも、お役に立てる内容です。
夫婦2人で老後5000万円は必要なのか、子供がいない老後でも幸せになれるのか、老後の楽しみ方をどう築いていけばよいのか。
この記事の後半では、60歳になったわたし(筆者)のケースについても赤裸々にお伝えします。

老後の不安や疑問を少しずつ一緒に考えていきましょう。
子なし夫婦の老後の面倒は誰が見てくれるのか?孤独の不安に向き合う

- 子なし夫婦の老後は本当に悲惨なのか?
- みじめな老後を迎える人に共通する落とし穴
- 老後の幸せを実現している子なし夫婦の特徴とは
- 住まいの選び方が将来の安心を左右する
子なし夫婦の老後は本当に悲惨なのか?
「子なし夫婦の老後は悲惨だよ」といった言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、結論から先に言うと、その一言に振り回される必要はありません。老後の姿は、人それぞれの価値観や準備の度合いによって大きく変わります。
たしかに、高齢になってからの病気や介護、死後の手続きなど、誰かの手を借りたくなる場面は出てくるかもしれません。でも、それは子どもがいても同じです。
むしろ最近では、「自分たちのことは自分たちで完結させたい」と考えている方も増えてきました。
子なし夫婦の中には、将来に備えて身元保証サービスや死後事務委任契約を結んでいる方、弁護士や司法書士など信頼できる第三者に相談しながら備えを整えている方も多くいらっしゃいます。
十分な資金と情報があれば、安心して年を重ねていくことは可能です。
また、自由な時間とお互いのペースで過ごす夫婦の老後は、穏やかで満ち足りたものにもなります。

「悲惨」という言葉は、必要以上に不安を煽るものです。大切なのは、自分たちに合った老後の形を見つけ、備えることだと考えています。
みじめな老後を迎える人に共通する落とし穴
なんとなく「自分だけ取り残されるかも…」という不安に駆られることがあるかもしれません。
実際に“みじめな老後”と感じてしまう背景には、いくつか共通するパターンがあります。
不安を放置して行動しない
将来のことに不安を感じていても、「なんとかなるかな」と思って準備を後回しにしてしまうと、いざという時に困ってしまうことも..。
少しずつでも準備を始めることが、不安を和らげる第一歩になります。
他人と比べて自分の暮らしを否定する
まわりに子どもや孫の話をする人がいると、自分たちと比べてしまうこともあります。でも、その人たちが本当に幸せなのかは分かりません。
他人と比べて落ち込むより、自分たちに合った幸せを大切にする方が、ずっと穏やかに過ごせます。
孤立を深めてしまう
「夫婦だけでいい」と閉じこもってしまうと、万が一どちらかが先に亡くなった時、孤独を深く感じる可能性があります。
趣味やボランティア、近所づきあいなど、ゆるやかなつながりを持つことは心の支えにもなります。
お金の準備不足
安心して暮らすためには、やはりある程度の資金は必要です。
とはいえ、莫大な金額が必要なわけではありません。毎月の生活費、医療や介護に備える費用、そして自分たちの「こう暮らしたい」という希望に合わせて、無理なく準備していくことが大切です。
情報を知らないままでいる
成年後見制度や死後事務委任契約、身元保証サービスといったものをご存知でしょうか、頼れる仕組みや制度は思っている以上にあります。
老後の幸せを実現している子なし夫婦の特徴とは
不安や孤独と隣り合わせに感じられがちな子なし夫婦の老後ですが、実際には笑顔で心豊かに暮らしている夫婦も多く存在します。
そうした夫婦に共通して見られるのは、 次にお伝えするような、ちょっとした心がけと柔軟な発想のようです。
自分たちらしい暮らし方を大切にしている
誰かの理想や「こうあるべき」にとらわれることなく、自分たちにとって心地よい時間を大切にしている姿が印象的です。
夫婦で同じ趣味を楽しんだり、日々の暮らしに小さな喜びを見つけたり。派手な生活ではなくても、丁寧に暮らす姿勢が満足感を生んでいます。
将来に向けた準備を早めに始めている
漠然とした不安をそのままにせず、早い段階から情報収集をし、身元保証や終活に取り組んでいるご夫婦は、気持ちの余裕も感じられます。
何から手をつけていいか分からない場合でも、まずは夫婦で話し合ってみることが出発点になります。
人とのつながりを大切にしている
近所の方とのちょっとした会話、趣味の教室、ボランティアなど。広く深くというよりも、気楽で心地よいつながりを持っていることで、孤独を感じにくくなります。
「頼り切る」ことではなく「助け合える」関係が築かれていることが多いのも特徴です。
お金の管理と見通しがしっかりしている
無理をせず、でも将来を見据えてしっかりと家計を整えている姿も見受けられます。
生活費、介護費、葬儀費などのシミュレーションを行い、いざという時に慌てないように備えています。計画があるだけで、心にゆとりが生まれるものです。
住まいの選び方が将来の安心を左右する
老後の暮らしで見落とされがちなのが「住まいの環境」です。
どこで、どんな風に暮らすかによって安心感は大きく変わります。体力や判断力が衰えてきた時に「住みにくい家」になってしまう前に、選び方のポイントを知っておきたいところです。
便利な立地に暮らす
高齢になればなるほど、徒歩圏内にスーパーや病院があることは大きな安心につながります。交通機関へのアクセスも含めて「買い物・通院・外出」のしやすさは重要です。
今は不便を感じなくても、将来のことを考えて場所選びをする人が増えています。
バリアフリー設計を意識する
段差が多い家や、階段しかない住まいは、年齢とともに負担が増えていきます。
安全に長く暮らすためには、スロープや手すりの設置、段差の解消などが整っていることが望ましいです。新築やリフォームの際には、先を見据えた設計がポイントです。
持ち家と賃貸の選び方
老後の住まいについては、「持ち家に住み続けるか」「賃貸に移るか」で悩む方も多くいます。
どちらが正解ということはなく、それぞれにメリットと注意点があります。
ここでは、持ち家と賃貸それぞれの特徴について見ていきまます。
なお、こちらのページでも持ち家が賃貸か、ということについて詳しく取り上げています。
持ち家のメリット
持ち家は長く住める安心感があり、ローン完済後は住居費を抑えられるのが魅力です。自分好みにリフォームもできるため、老後の暮らしに合わせた環境作りがしやすいです。
賃貸のメリット
身軽に住み替えができることが魅力で、介護施設への移行などにも柔軟に対応できます。また、建物の修繕責任も大家側にあるため、高齢期には助かる点もあります。
老後に向けた住み替えのタイミング
「いざ」という時に慌てて引っ越すのではなく、元気なうちに住み替える人も増えています。体が動く今だからこそできる選択や準備があるからです。
住まいは毎日の安心と快適さに直結するため、将来の暮らしを左右する大切な要素のひとつです。
こちらの記事では、子なし夫婦にとって賃貸か持ち家がいいかについて書いています。よろしければご参照ください。
子なし夫婦の老後の面倒を自分たちで!今から始めたい準備

- 頼れる身元保証サービスや後見制度とは?
- 兄弟や甥姪に迷惑をかけずに済む対策
- 老後資金や住まい選びで押さえておきたいポイント
- 夫婦ふたりの最期をどう迎える?わたし達の考え
頼れる身元保証サービスや後見制度とは?
老後を迎えるにあたって、手術の同意や入院時の手続き、介護施設への入居など、家族の代わりに対応してくれる人が必要になる場面が増えてきます。
そんなとき、子なし夫婦にとって心強い存在となるのが「身元保証サービス」や「後見制度」です。
信頼できる第三者や専門機関とつながることで、自分らしく安心して暮らしていく道がひらけます。
身元保証サービスの役割
身元保証サービスは、病院や介護施設に入るときの「保証人」となってくれる民間のサポート制度です。
高齢者の一人暮らしや、身寄りの少ない夫婦にとっては、こうしたサービスがあることで、施設の選択肢が広がり、将来への備えにもなります。
成年後見制度について
将来、判断力が低下したときに備えて、自分の意思を代弁してくれる制度として「成年後見制度」があります。
財産管理や契約手続きなど、日常生活を支える重要な役割を果たしてくれる仕組みです。
[参照]成年後見制度の詳細や申し立て方法は、法務省の公式パンフレットがわかりやすく整理されています。
法務省「成年後見制度パンフレット(いざという時のために 知って安心」https://www.moj.go.jp/content/001434006.pdf
法定後見と任意後見
法定後見は、すでに判断能力が不十分になってから家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
一方、任意後見は元気なうちに信頼できる人と契約を交わし、将来の支援をあらかじめ準備するスタイルです。
後見制度利用のポイント
後見制度を利用する際は、どこまでサポートしてもらえるのか、費用はどれくらいかかるのかを事前に確認することが大切です。
行政書士や弁護士など専門家に相談することで、自分たちに合った形を見つけやすくなります。
兄弟や甥姪に迷惑をかけずに済む対策
「いざという時、頼れる人がいない。でも身内にも迷惑はかけたくない」。そう思う方は少なくありません。
身近な親族に頼る選択肢もありますが、相手にとっても負担となる可能性を考えると、事前にしっかり準備しておきたいところです。
死後事務委任契約を活用する
葬儀や遺品整理、行政手続きなど、亡くなった後に必要となる事務を代行してもらう制度です。信頼できる専門家や団体と契約を結ぶことで、身内に頼らずとも最期まで安心して生きる道を整えられます。
エンディングノートの活用
法的な効力はありませんが、自分の希望や大切にしたいことを明文化することで、万一のときにも周囲が困らずにすみます。「どこに何があるか」「誰に連絡してほしいか」などをまとめておくことで、見送る人への負担も軽くなります。
第三者への信託・委任契約
信託銀行や専門の団体、または弁護士などに財産の一部や手続きを委託する方法もあります。契約によって具体的な範囲や内容を調整できるため、より柔軟で確実な対策が可能になります。
頼れる人がいないと感じるときは
「誰にも頼れない」と感じてしまうと不安はどんどん膨らんでしまいます。まずは地域包括支援センターや専門機関など、相談できる場所に声をかけてみることが大切です。
気持ちが少しでも楽になる第一歩になるかもしれません。
老後資金や住まい選びで押さえておきたいポイント
安心して暮らしていくためには、「お金」と「住まい」、この2つの準備が欠かせません。
どちらも無理のない範囲で、でも確実に備えておくことで、将来の不安がずっと軽くなります。
そこで、老後資金と住まい選びに関する大切なポイントを整理しておきます。
老後資金の基本的な考え方
老後の生活に必要な金額は、人それぞれのライフスタイルによって違います。ただ、目安となる金額や考え方を知っておくことで、自分たちに必要な備え方が見えてきます。
最低限必要な生活費の目安
公的年金だけでは足りないと感じる方が多く、ゆとりある老後を送るためには月に25万〜30万円程度を想定しているケースもあります。生活費のほかに、医療費や介護費も考慮しておくと安心です。
予備資金の準備
急な入院や介護サービスの利用、施設入居などには一時的に大きな出費が必要になることもあります。そうした事態に備えて、少し余裕を持った貯蓄を意識すると気持ちにもゆとりが生まれます。
住まい選びで意識したいこと
暮らしの基盤となる住まいは、安心して年を重ねるためにとても重要です。場所や設備、将来の住み替えも視野に入れながら、柔軟に考えていくことが大切です。
アクセスのよい立地を選ぶ
通院や買い物の利便性、公共交通機関へのアクセスなど、年齢とともに重視すべき点は変わってきます。将来を見据えて、「通いやすさ・暮らしやすさ」で選ぶことがポイントです。
バリアフリーを意識した環境
手すりや段差の少ない設計、エレベーターの有無など、高齢になってからも安全に過ごせる設備が整っているかどうかも重要です。
住み慣れた場所で安心して暮らすには、環境の工夫が必要になります。
将来の住み替えを想定しておく
今は元気でも、介護が必要になる可能性を考えると、将来の住み替え先についても視野に入れておくと安心です。
サービス付き高齢者住宅や介護施設など、自分たちの希望に合った選択肢を早めに調べておくことがおすすめです。
夫婦ふたりの最期をどう迎える?わたし達(筆者)の考え
私たち夫婦が老後について真剣に考えはじめたのは、実は最近のことです。
それまでは何となく先延ばしにしてきたのですが、ある本との出会いがきっかけとなりました。
読んだのは『おふたりさまの老後は準備が10割』という本です。
この本を通じて、老後とは「いつかやってくる遠い話」ではなく、「今から向き合っておくべき現実」なのだと感じるようになりました。
私自身、一人っ子であることもあり、両親の将来についても無関係ではいられません。
自分たち夫婦の老後と、両親の老後。その両方を意識するようになったこの1年は、とても大きな気づきの時間になりました。
住まいに関しては、こちらの記事でも少し触れましたが、私たちはマンションを購入したり、新たに家を建てたりするつもりはありません。今住んでいる賃貸で暮らし続ける予定です。
そして、もう少し年齢を重ねて、体力や健康に不安を感じるようになったタイミングで「次の住まい」を決めようと考えています。
その選択肢のひとつとして、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)についても情報収集を進めています。終の棲家になる可能性が高いからこそ、納得できる選択をしたいと思っています。
住まいのことだけでなく、いざという時に親族に頼る場面も出てくるかもしれません。現時点では、夫の姪や私の母方の親族が候補に挙がっています。
ただし、きちんと話し合いをしてはいないため、数年以内に一度しっかり向き合う必要があると感じています。
よく「子供がいないと老後が大変」と言われることがありますが、最近は子供がいても頼れない家庭も少なくありません。子なしだからといって、老後が必ずしも悲惨になるとは限らない。そう実感しています。
それでも、何かあった時に「最終的には子供がいるから大丈夫」と思えることが、心理的な安心感につながっているのも事実だと思います。

だからこそ、子供がいる人から「子なしは面倒を見てもらえない」といったような言葉を受けた時には、それをそのまま否定せず、「そういう考え方もあるよね」と受け止め、必要以上に反論しないことが、自分自身の心の平和にもつながるような気がしています。
【まとめ】子なし夫婦の老後の面倒を乗り越えるために知っておきたいこと
今回の記事のまとめです。
- 子なし夫婦の老後が悲惨とは限らず、準備次第で安心できる
- 不安を放置せず、早めに行動することが将来の安心につながる
- 他人と比較せず、自分たちらしい暮らしを大切にする
- 孤立を防ぐために、地域や趣味など人とのつながりを持つ
- 生活費や医療費などの老後資金をシミュレーションして備える
- 成年後見制度や死後事務委任契約などを活用して自立を支える
- 身元保証サービスは施設入居や医療手続き時の支援になる
- サ高住などの住み替え先は元気なうちから検討しておく
- 便利な立地やバリアフリーの住環境が老後の安心に直結する
- 持ち家と賃貸にはそれぞれのメリットがあり、柔軟に考える
- エンディングノートで自分の希望をまとめておくと周囲の負担が減る
- 信託や委任契約で第三者に支援を任せる選択肢もある
- 親族に頼る場合は早めに話し合っておくことが大切
- 子あり・子なしに関係なく、老後の安心は自ら備えることで得られる
- 他人の言葉に左右されず、自分たちの幸せな老後を描いていく意識が大切
今回の記事、お役に立てたら嬉しいです。
ありがとうございました。
【法律一般に関する免責】
当サイトは個別の法律相談を行うものではありません。
具体的な法的手続きや権利義務については、弁護士・司法書士・行政書士などの有資格者 にご相談ください。
こちらの記事もどうぞ♪